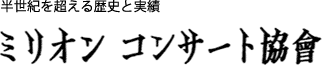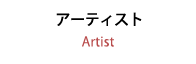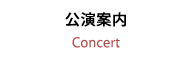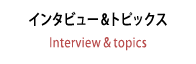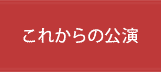アプサラス 第5回演奏会
~弦楽オーケストラをめぐる新たなる“息吹”、そして確かなる “風”~
| 日時 |
2015年3月26日(木)19時 |
|---|---|
| 会場 | 東京文化会館 小ホール(東京・上野) |
| 料金 | 全自由席 ¥3,500 |
| 出演 |
指揮:野津如弘 チェンバロ:大塚直哉 弦楽アンサンブル“TGS(東京芸大ストリングス)”(コンサートミストレス:長尾春花) |
| 曲目 |
菊池幸夫/チェンバロ協奏曲(2015新作初演) 正門憲也/弦楽の舟歌からⅡ(2007)、Ⅲ(2015初演) 平井正志/弦楽の為の「プロムナード3」(新作初演) 長谷川勉/弦楽のための楽章(改訂初演) 松村禎三/弦楽のためのプネウマ(1987) |
|
[主催] アプサラス http://www.t-apsaras.jp/ [助成] (公財)朝日新聞文化財団 [後援] (社)日本作曲家協議会 日本現代音楽協会 日本ロシア音楽家協会 [チケット取扱い] ローソンチケット TEL.0570-000407(オペレーター対応10時〜20時) [Lコード:34425 TEL.0570-084-003(関東地区)] 東京文化会館チケットサービス TEL.03-5685-0650 ミリオンコンサート協会 TEL.03-3501-5638 [お問合せ] アプサラス事務局 TEL.& FAX.03-3488-9292 E-mail:info@t-apsaras.jp | |
アプサラスについて
松村禎三氏は2007年8月6日にその78年の生涯を閉じました。私たちは氏の業績を讃え、作品を世に広めると共に、その遺志を継ぎ、新たな創作・演奏活動を通して音楽芸術の新境地を拓くべく、志を同じくする者による会《アプサラス》を2008年に設立しました。会名の《アプサラス》は、氏の作品《アプサラスの庭》より謹んで頂戴致しました。
主な活動には、2008年アプサラス第1回演奏会〜松村禎三(1929〜2007)室内楽作品展〜、2009年アプサラス第2回演奏会〜歌とピアノと弦楽器の夕べ〜、2012年アプサラス第3回演奏会『松村禎三 作曲家の言葉』の出版を記念して〜作曲家とテクストが対峙する合唱空間〜アプサラスが地平を拓く、2013年アプサラス第4回演奏会〜狛江から世界の松村禎三へ〜児童合唱から映画の音楽、そして孤高の世界へ、を開催などがあります。『松村禎三 作曲家の言葉』(2012春秋社刊)の出版にあたりましては、資料収集等の準備を行いました。
作曲家プロフィール
■松村禎三 Teizo Matsumura/Composer
1929年京都市生まれ。旧制第三高等学校理科卒業。伊福部 昭、池内友次郎の両氏に師事。1955年「序奏とアレグロ」がNHK毎日音楽コンクール作曲部門第1位を受賞、デビュー作となる。
サントリー音楽財団委嘱による遠藤周作の小説に基づくオペラ「沈黙」では毎日芸術賞、モービル音楽賞、京都音楽賞大賞を受賞。その他、尾高賞、芸術祭優秀賞など受賞作も多数。映画音楽、劇音楽の分野でも多くの作品を残している。2007年8月6日逝去。
■長谷川勉 Tsutomu Hasegawa/Composer
東京藝術大学卒業、同大大学院修了。石桁真礼生、松村禎三両氏らに師事。ウィーン国立音楽大学に留学、作曲、指揮をF.ツェルハ、O.スウィトナーらに学ぶ。ウィーン国際管弦楽コンクール第2位(1位なし)、ヒッツァッカー作曲コンクール第1位及び聴衆賞等を受賞。オーストリア政府給費生。
横浜国立大学、東京藝術大学非常勤講師、鹿児島大学教授等を経て、現在、山形大学地域教育文化学部教授。
■平井正志 Masashi Hirai/Composer
1957年東京生まれ。80年東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、82年同大大学院音楽研究科修士課程作曲専攻修了。これまでに作曲を松本民之助、松村禎三、池野 成の各氏に師事。2003年5月29日に自作の室内楽作品展を開催。
現在、桐朋学園芸術短期大学非常勤講師、(財)ヤマハ音楽振興会JOC創作講座講師。日本ロシア音楽家協会会員。アプサラス会員。
主要作品に"Boundary" for Orchestra、"REMINISCENCE" for Chamber orchestra、木管五重奏曲、Piano sonata、「梢 ―三つの素描―」等がある。
■菊池幸夫 Yukio Kikuchi/Composer
1964年東京都生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒、同大大学院修了。作曲を北村 昭、佐藤 眞、松村禎三各氏に師事。
第14回日本交響楽振興財団作曲賞入選、第3回芥川作曲賞を受賞。これまで管弦楽作品が、東響、新日本フィル、読売日響、オーケストラ・アンサンブル金沢などにより演奏される。また、吹奏楽曲や室内楽曲も多く手掛けている。
現在、日本作曲家協議会、日本ロシア音楽家協会、アプサラス各会員。エリザベト音楽大学准教授、国立音楽大学非常勤講師。
■正門憲也 Kenya Masakado/Composer
西宮高校音楽科Violin科、東京藝術大学作曲科卒業、同大大学院作曲専攻修了。第59回日本音楽コンクール作曲部門2位。第15回日本交響楽振興財団作曲賞入選など。Violinを故東儀 幸、日高 毅、作曲を池上 敏、藤島昌壽、佐藤 眞、近藤 讓、故三善 晃の各氏に師事。
近作は、管弦楽の舟歌(2009)、遊戯18番「浮舟」(09 Fl・Vc・Pf)、遊戯第19番「木霊」(11 Vc Ensemble)、3つのClarinetの舟歌(12)、弦楽四重奏曲第3番「遊戯」(14)など。
出演者プロフィール
■野津如弘(指揮) Yukihiro Notsu/Conductor
仙台生まれ。早稲田大学第一文学部卒。東京藝術大学楽理科を経て、日本人として初めてフィンランド国立シベリウス音楽院指揮科に入学。レイフ・セーゲルスタム、ヨルマ・パヌラの両氏に師事。2008年、同音楽院修士課程を最高位で修了。マスタークラスにおいてサー・コリン・デイヴィス、ベルナルト・ハイティンク、ネーメ・ヤルヴィの諸氏に学ぶ。
これまでにフィンランド放送響、トゥルク・フィルハーモニー管、クオピオ響、ラ・テンペスタ室内管等、フィンランド主要オーケストラ及び群響などに客演。フィンランドで邦人作品の初演を多く手がける他、愛知県立芸術大学及び常葉大学で後進の指導にも当たっている。
■大塚直哉(チェンバロ) Naoya Otsuka/Cembalo
東京藝術大学楽理科を経て同大大学院チェンバロ科、アムステルダム音楽院チェンバロ科およびオルガン科を修了。チェンバロ、オルガン、クラヴィコードの奏者として活発な活動を行うほか、これらの楽器に初めて触れる人のためのワークショップを各地で行っている。
東京藝術大学准教授、国立音楽大学非常勤講師。宮崎県立芸術劇場、彩の国さいたま芸術劇場、台東区旧奏楽堂のオルガン事業アドヴァイザー、アンサンブル・コルディエ音楽監督、日本チェンバロ協会副会長を務める。NHK-FMの朝の番組「古楽の楽しみ」に案内役として出演中。
■弦楽アンサンブル“TGS(東京芸大ストリングス)” Tokyo Geidai Ensemble/String Ensemble
東京藝術大学2008年入学の同期生を中心に編成される弦楽アンサンブル。東京藝術大学弦楽科の澤 和樹氏(ヴァイオリン)、川崎和憲氏(ヴィオラ)といった教授陣が学生時代に自主的に結成していた「ラーチェロ室内合奏団」の活動を知ったことが結成のきっかけとなった。
2011年3月6日、川口市民会館において催された「第22回 小さな音楽会 ~弦楽合奏のたのしみ~」を期に、発足。指揮者なしの弦楽合奏スタイルで、バロックからロマン派、日本の作曲家による現代作品、ポップスに至るまでの幅広いレパートリーを持ち、自主公演、委託公演、震災の復興支援活動としての演奏、地方・海外への遠征公演など、精力的に活動を展開中。
松村禎三氏は2007年8月6日にその78年の生涯を閉じました。私たちは氏の業績を讃え、作品を世に広めると共に、その遺志を継ぎ、新たな創作・演奏活動を通して音楽芸術の新境地を拓くべく、志を同じくする者による会《アプサラス》を2008年に設立しました。会名の《アプサラス》は、氏の作品《アプサラスの庭》より謹んで頂戴致しました。
主な活動には、2008年アプサラス第1回演奏会〜松村禎三(1929〜2007)室内楽作品展〜、2009年アプサラス第2回演奏会〜歌とピアノと弦楽器の夕べ〜、2012年アプサラス第3回演奏会『松村禎三 作曲家の言葉』の出版を記念して〜作曲家とテクストが対峙する合唱空間〜アプサラスが地平を拓く、2013年アプサラス第4回演奏会〜狛江から世界の松村禎三へ〜児童合唱から映画の音楽、そして孤高の世界へ、を開催などがあります。『松村禎三 作曲家の言葉』(2012春秋社刊)の出版にあたりましては、資料収集等の準備を行いました。
作曲家プロフィール
■松村禎三 Teizo Matsumura/Composer
1929年京都市生まれ。旧制第三高等学校理科卒業。伊福部 昭、池内友次郎の両氏に師事。1955年「序奏とアレグロ」がNHK毎日音楽コンクール作曲部門第1位を受賞、デビュー作となる。
サントリー音楽財団委嘱による遠藤周作の小説に基づくオペラ「沈黙」では毎日芸術賞、モービル音楽賞、京都音楽賞大賞を受賞。その他、尾高賞、芸術祭優秀賞など受賞作も多数。映画音楽、劇音楽の分野でも多くの作品を残している。2007年8月6日逝去。
■長谷川勉 Tsutomu Hasegawa/Composer
東京藝術大学卒業、同大大学院修了。石桁真礼生、松村禎三両氏らに師事。ウィーン国立音楽大学に留学、作曲、指揮をF.ツェルハ、O.スウィトナーらに学ぶ。ウィーン国際管弦楽コンクール第2位(1位なし)、ヒッツァッカー作曲コンクール第1位及び聴衆賞等を受賞。オーストリア政府給費生。
横浜国立大学、東京藝術大学非常勤講師、鹿児島大学教授等を経て、現在、山形大学地域教育文化学部教授。
■平井正志 Masashi Hirai/Composer
1957年東京生まれ。80年東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、82年同大大学院音楽研究科修士課程作曲専攻修了。これまでに作曲を松本民之助、松村禎三、池野 成の各氏に師事。2003年5月29日に自作の室内楽作品展を開催。
現在、桐朋学園芸術短期大学非常勤講師、(財)ヤマハ音楽振興会JOC創作講座講師。日本ロシア音楽家協会会員。アプサラス会員。
主要作品に"Boundary" for Orchestra、"REMINISCENCE" for Chamber orchestra、木管五重奏曲、Piano sonata、「梢 ―三つの素描―」等がある。
■菊池幸夫 Yukio Kikuchi/Composer
1964年東京都生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒、同大大学院修了。作曲を北村 昭、佐藤 眞、松村禎三各氏に師事。
第14回日本交響楽振興財団作曲賞入選、第3回芥川作曲賞を受賞。これまで管弦楽作品が、東響、新日本フィル、読売日響、オーケストラ・アンサンブル金沢などにより演奏される。また、吹奏楽曲や室内楽曲も多く手掛けている。
現在、日本作曲家協議会、日本ロシア音楽家協会、アプサラス各会員。エリザベト音楽大学准教授、国立音楽大学非常勤講師。
■正門憲也 Kenya Masakado/Composer
西宮高校音楽科Violin科、東京藝術大学作曲科卒業、同大大学院作曲専攻修了。第59回日本音楽コンクール作曲部門2位。第15回日本交響楽振興財団作曲賞入選など。Violinを故東儀 幸、日高 毅、作曲を池上 敏、藤島昌壽、佐藤 眞、近藤 讓、故三善 晃の各氏に師事。
近作は、管弦楽の舟歌(2009)、遊戯18番「浮舟」(09 Fl・Vc・Pf)、遊戯第19番「木霊」(11 Vc Ensemble)、3つのClarinetの舟歌(12)、弦楽四重奏曲第3番「遊戯」(14)など。
出演者プロフィール
■野津如弘(指揮) Yukihiro Notsu/Conductor
仙台生まれ。早稲田大学第一文学部卒。東京藝術大学楽理科を経て、日本人として初めてフィンランド国立シベリウス音楽院指揮科に入学。レイフ・セーゲルスタム、ヨルマ・パヌラの両氏に師事。2008年、同音楽院修士課程を最高位で修了。マスタークラスにおいてサー・コリン・デイヴィス、ベルナルト・ハイティンク、ネーメ・ヤルヴィの諸氏に学ぶ。
これまでにフィンランド放送響、トゥルク・フィルハーモニー管、クオピオ響、ラ・テンペスタ室内管等、フィンランド主要オーケストラ及び群響などに客演。フィンランドで邦人作品の初演を多く手がける他、愛知県立芸術大学及び常葉大学で後進の指導にも当たっている。
■大塚直哉(チェンバロ) Naoya Otsuka/Cembalo
東京藝術大学楽理科を経て同大大学院チェンバロ科、アムステルダム音楽院チェンバロ科およびオルガン科を修了。チェンバロ、オルガン、クラヴィコードの奏者として活発な活動を行うほか、これらの楽器に初めて触れる人のためのワークショップを各地で行っている。
東京藝術大学准教授、国立音楽大学非常勤講師。宮崎県立芸術劇場、彩の国さいたま芸術劇場、台東区旧奏楽堂のオルガン事業アドヴァイザー、アンサンブル・コルディエ音楽監督、日本チェンバロ協会副会長を務める。NHK-FMの朝の番組「古楽の楽しみ」に案内役として出演中。
■弦楽アンサンブル“TGS(東京芸大ストリングス)” Tokyo Geidai Ensemble/String Ensemble
東京藝術大学2008年入学の同期生を中心に編成される弦楽アンサンブル。東京藝術大学弦楽科の澤 和樹氏(ヴァイオリン)、川崎和憲氏(ヴィオラ)といった教授陣が学生時代に自主的に結成していた「ラーチェロ室内合奏団」の活動を知ったことが結成のきっかけとなった。
2011年3月6日、川口市民会館において催された「第22回 小さな音楽会 ~弦楽合奏のたのしみ~」を期に、発足。指揮者なしの弦楽合奏スタイルで、バロックからロマン派、日本の作曲家による現代作品、ポップスに至るまでの幅広いレパートリーを持ち、自主公演、委託公演、震災の復興支援活動としての演奏、地方・海外への遠征公演など、精力的に活動を展開中。